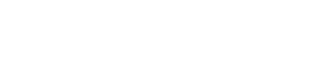本文
第47回 如願寺と如願寺谷

如願寺と如願寺谷
寺伝によると、如願寺は、万寿元年(一〇二四)に比叡山の僧・皇慶が、行基菩薩作の薬師如来像を背負ってこの地に到り、お堂を建てて安置したのが始まりと伝えられています。
旧宮津城下町では最古の創建伝承をもつ古刹です。
江戸時代以前の様子は、不明な点が多いですが、如願寺の境内には正和元年(一三一二)銘の五輪塔や、明徳五年( 一三九四) 銘をもつ宝篋印塔が残され、宮津地区の中世を考える上で注目されます。
永正三年(一五〇六)、若狭武田氏の丹後侵攻に際しては、「如願寺跡」において丹後国守護・一色氏の配下である小倉氏と若狭武田氏の戦いが行われました。如願寺川南側の題目山の中腹には、宮津山(如願寺山)城跡がみられ、中世にさかのぼる城跡と考えられています。
如願寺は、宮津から加悦谷(石川)に至る地蔵峠の入り口に位置することから、中世には交通の要衝として重要な位置を占めたと評価できます。
現存する本堂は、細川氏により「仮堂」が建てられた後、永井氏によって本格的再建されたとされています。また、山門には雲慶作の仁王像が安置されていたと伝えられますが、貞享三年(一六八六)の火災で焼失し、その後に再建されています。
昭和初期には、現在より広い敷地を誇りましたが、昭和二七年、鉄道の横に建つ山門現在地に移築。現在の景観の原型が形成されました。