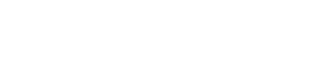本文
みやづ歴史紀行(162回)
高石寺と地蔵菩薩坐像
日置上集落にある金剛心院の境内には、石造地蔵菩薩坐像が安置されています。この像は、金剛心院の南西二〇〇m離れた場所に位置する小字高石の丘陵にかつてあった地蔵堂に祀られていたものです。
金剛心院に伝わる寺伝によれば、この地にはかつて高石寺(こうしゃくじ)という名の寺院が存在し、金剛心院の塔頭であったとされます。金剛心院の寺伝には、勅使が金剛心院を訪れる際、まず高石寺で駕籠(かご)を降り、装束を整えてから向かったという記述も見られます。しかし、江戸時代には高石寺は衰退し、地蔵堂だけが残されました。文化十四年(一八一七)の『書上帳』には、地蔵堂には地蔵菩薩像と忍性(にんしょう)上人像が安置されていたものの、周囲は木々に覆われていた様子が記録されています。その後、明治三十一年(一八九八)の地蔵堂再建時に作成された『勧進帳(かんじんちょう)』には、この地蔵尊が「稲の病除けの地蔵」として広く信仰され、田植えの後には遠方からも多くの参詣者が訪れていたことが記されています。
地蔵菩薩坐像は花崗岩製で、像高一六七cm。船形光背(ふながたこうはい)を背に、右手に錫杖(しゃくじょう)を持ち、蓮華座に坐す姿が表されています。本体は台座上部と光背(こうはい)を含めて一石の花崗岩から彫り出されており、光背の左右には「嘉暦(かりゃく)四年六月廿四日(二十四)」「戸□□坊」という銘文(めいぶん)が刻まれ、鎌倉時代の嘉暦四年(一三二九)の作であることが分かります。相貌や体躯(たいく)には摩耗(まもう)が見られるものの制作年代が明確な点でも非常に貴重な遺品といえます。
また、伝承によると、本像は金剛心院の中興の祖・忍性の手による像と伝わります。忍性は、摂津・四天王寺の再興に際し、石鳥居を建造しますが、本像はその余材から造られたと伝わります。しかし、忍性は嘉元元年(一三〇三)に没しており、この伝承の信憑性には疑問もあります。ただし、その後の建武元年(一三三四)の丹後国分寺再建をはじめ、丹後地域における律宗西大寺派の活動が盛んであったことを踏まえると、このような伝承は、西大寺派の活動の広がりを示すものとして注目されます。
 石造地蔵菩薩坐像(高石地蔵)
石造地蔵菩薩坐像(高石地蔵)
(宮津市教育委員会)