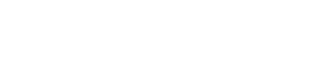本文
みやづ歴史紀行(161回)
妙円寺の庭園
日置浜地区に所在する妙円寺は、本堂や庫裏(くり)の北側に庭園が広がります。水辺の景観美を表現した池泉庭園(ちせんていえん)で、庫裏の奥座敷からの鑑賞を意識した配置となっています。
この庭園は、江戸時代後期に妙円寺第十九世・日妙(にちみょう)上人によって作庭されたと伝えられています。中央の池は琵琶湖を象(かたど)り、その周囲には「近江八景」を配した構成となっています。「近江八景」とは、中国の瀟湘八景(しょうしょうはっけい)にちなんで、十七世紀に選定された琵琶湖周辺の景勝地で、日本における八景の端緒となりました。琵琶湖は天橋立と並び、古くから名所として知られており、江戸時代に「近江八景」は、国指定名勝である彦根城の「玄宮園(げんきゅうえん)」をはじめ、多くの池泉庭園に取り入れられました。妙円寺庭園も、『日置村誌』に「八景園」の名称で紹介され、「誇るべき庭園」と讃えられています。
妙円寺庭園は、「形式化が進んだ江戸時代末期の庭園にあって、荒削りながらも作庭者の創意に富んだ個性が感じられる優れた作例」として、昭和五十九年(一九八四)に京都府の名勝に指定されました。『京都府の文化財』(京都府教育委員会、一九八四年)では、妙円寺庭園の築山や石橋の配置などの空間構成について紹介されており、特に石組や鑑賞視点の工夫に関して、「築山には大ぶりの岩を多数用いた豪快な石組が施され、創意ある景観を見せている」「琵琶湖を象ったとされる池は、座敷側からは一見単純な形に見えるが、築山を巡るように変化しており、鑑賞者の視点移動を意識した、躍動感のある地割となっている」などと高く評価されています。
指定から四十年以上が経過した現在も、寺院や檀家の尽力により、築山や石組の損傷は少なく、良好な状態が保たれています。
(宮津市教育委員会)