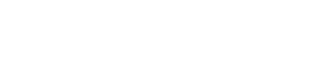本文
みやづ歴史紀行(159回)
日置地区の中世山城
日置地区には、日置上城跡と日置浜城跡の二つの山城跡があり、日置地区の平野や宮津湾を一望することができます。二つの城跡には、平坦地である曲輪(くるわ)や防御設備の痕跡が見られ、当時の名残を色濃く残します。有事の際は敵を迎え撃つ防衛拠点として機能したと考えられます。
日置上城跡は、日置上集落北側の世屋川と畑川に挟まれた丘陵上に位置し、麓(ふもと)には日置氏の菩提寺である禅海寺(ぜんかいじ)が建ちます。遺構は、標高八〇メートルと一五〇メートルの東西の山頂部に二カ所遺されており、それぞれ五〇〇メートル程離れた場所に位置します。東側の城跡は、山頂部の主郭(しゅかく)を中心に帯曲輪をめぐらし、北と西と南東の三方向の尾根上には曲輪と防御設備である堀切を配します。西側の城跡には、山頂部の主郭西側及び南側の斜面に、畝状空堀群(うねじょうからぼりぐん)が設けられており、堅固な構造となっています。また、主郭東側の尾根上には比高差の少ない曲輪が連続して見られます。城主の伝承としては、室町時代後期に編纂(へんさん)された『丹後国御檀家帳』に「日置殿の御城山」の名が、江戸時代に編纂された『丹後旧事記』には、「日置小次郎」などの伝承が記されています。麓の禅海寺の存在も合わせて、日置氏の本拠地であったと考えられます。
日置浜城跡は、宮津湾に面する向山(妙見山(みょうけんざん))にその痕跡が遺されています。現在は妙見堂が建つ山頂が主郭と考えられ、周囲には曲輪が見られます。城主の伝承としては、『丹後国御檀家帳』に「ひをきむこ山の御城」に「一宮殿をとな」の「杉左馬亮(すぎさまのすけ)」と記されています。一宮殿は府中を本拠とした丹後国守護の一色氏と考えられ、杉左馬亮は一色氏家臣の中でも「をとな(大人)」という表記から有力な家臣だったと推察されます。他に江戸時代の地誌類には、倉内将監(くらうちしょうげん)や日置弾正(ひおきだんじょう)の名前が伝えられています。
両集落に築かれた二つの山城は、現在は長い年月を経て草木に覆われています。しかし、山に残る堅固な防御設備の痕跡は、戦乱時代の日置地区の一幕を今日に伝えます。
(宮津市教育委員会)

(日置地区の山城の位置)