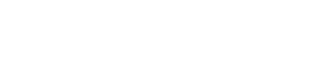本文
みやづ歴史紀行(156回)
禅海寺の み仏たち
禅海寺は、日置上(あげ)集落の高台に位置する寺院です。寺伝によると、九世紀後半の創建とされ、元は寿福寺という名の天台宗の寺院であったと伝えられています。往時は七堂伽藍を備えた広大な境内を擁していましたが、度重なる戦乱の中で荒廃し、至徳年間(一三八四~八七)に東福寺の明江和尚により中興され臨済宗寺院となりました。この時、この地の景色が中国の百丈山を彷彿させることから、百丈山禅海寺の名に改められたと伝えられています。
寺院には、中世に遡る数多くの仏教美術が伝来しています。特に本尊の阿弥陀如来坐像とその両脇侍である勢至菩薩立像、観音菩薩立像に千手観音菩薩立像を加えた四躯の仏像は、いずれも十二世紀後半の製作とみられています。
阿弥陀如来坐像と両脇侍像(りょうきょうじぞう)は、来迎印を結ぶ阿弥陀如来坐像を中心に、蓮茎を執る両脇侍像を配する三尊形式をとります。三躯とも身体各部の整ったロポーションや衣文の表現など平安時代から鎌倉時代へ移行する過渡的な様式をよく示す優品として知られています。
一方、千手観音菩薩立像は、頭髪の表現や、衣類の彫法などから三尊像と比較してより洗練された様式が見られ、製作年代も少し遡るものと考えられます。また、本像は、元は本堂で安置されている毘沙門天立像(びしゃもんてんりゅうぞう)及び不動明王立像を脇侍とした三尊形式で祀られていました。観音菩薩の脇侍として不動明王と毘沙門天を配する形式は、比叡山横川中堂で成立して以降、天台系の寺院に見られます。脇侍の二尊は、室町時代の製作と見られ、千手観音像の製作年代とは開きがありますが、三尊形式での伝来過程も含め天台寺院であった名残を残します。
この禅海寺に伝来する四躯の仏像は、何(いず)れも当時の丹後における信仰を物語る優品として、国の重要文化財に指定されています。平安時代より寺院と地元の人々により守り伝えられる中で、中世の日置で育まれた信仰を今に伝えます。
(宮津市教育委員会)