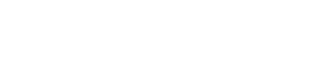本文
みやづ歴史紀行(155回)
日置地区の変遷
日置地区は、宮津市西北部に位置し、東側は宮津湾に面し、対岸に栗田半島を望みます。養老地区との境には、弥助山が海に突き出るように聳そびえ、山塊により沿岸部の浸食が遮られることから、畑川・世屋川の下流域には沖積平野が発達します。海岸部には砂浜が見られ日置浜はま集落が立地します。その後背湿地には水田が広がり、山裾の扇状地の高台には日置上あげ集落が展開します。
水稲耕作に適した地形であることから、弥生時代に遡る遺跡も多くみられ、早くから農耕集落が成立したと考えられています。古代・中世には日置郷に属していたと考えられ、日置上集
落の金剛心院と禅海寺には、平安時代から鎌倉時代の仏像彫刻の優品が伝来するほか、南北朝時代には、御家人の日置末清が足利高氏(尊氏)の軍勢に参加するなど古くから歴史の舞台となりました。
室町時代に成立したとみられる『丹後国御檀家帳』には、「ひをき田中むら」、「ひをきくわ田村」、「日置竹森村」など現在も伝わる地名が見られ、江戸時代の『延宝三年郷村帳』には「日置上村」、「日置濱村」の名が登場します。農業を生業とした日置上村に対して、日置浜村は畑川、世屋川を通じて集積した世屋地区の炭や薪を、宮津城下町へと運ぶ物流拠点となり、廻船による交易に携わるとともに、違法な木材取引を取り締まりました。また、日置上村と日置浜村の境界に生野代官所の出張陣屋が置かれ、享保四年(一七一九)に湊宮村(京丹後市久美浜町)へ代官所が移るまでの間、一時は幕府領となりました。
明治時代に入り、日置上村と日置浜村が合併し、明治二十二年(一八八九)の町村制の施行により日置村となりました。戦後、昭和二十九年(一九五四)に宮津市となり現在に至ります。
(宮津市教育委員会)