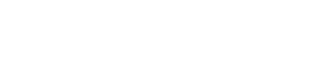本文
みやづ歴史紀行(153回)
松尾集落の歴史と信仰
松尾集落は、上世屋集落から世屋川を挟んだ対岸に位置します。日置浜と野間を結ぶ野間街道の通過地点に立地しており、明治二十年(一八八七)には四十戸に及ぶ戸数がありました。宮津湾を望む傾斜地一面には、棚田が広がり、令和四年(二〇二二)には上世屋の棚田と共に「上世屋・松尾の棚田」として農林水産省の「つなぐ棚田遺産」に認定されました。
集落背後には、標高三八七mの朝日岳(あさひだけ)があります。戦国時代には、松尾城が築かれ、一色氏の家臣である坂野四郎左衛門(さかのしろうざえもん)が城主として伝えられています。現在も山頂には二段の曲輪(くるわ)(平坦地)や堀切など山城の痕跡が残されています。
また、朝日岳の頂上には、修験道(しゅげんどう)の開祖と伝えられる役行者(えんのぎょうじゃ)(役小角 (えんのおづの))を祀る行者堂が建ちます。修験道とは、山岳信仰に仏教や道教などの要素が混じった宗教であり、修行者は険しい山で修行を積みながら、神秘的な力を修得することを目指したとされています。毎年四月十八日の山開きから八月十八日までの間、堂舎の戸が開かれ集落内外からの信者が参拝に訪れました。元は、朝日岳に隣接する大ブナ山の山頂にありましたが、明治時代に現在の地へと移されました。現在でも大ブナ山には旧行者堂の石垣が残されています。
朝日岳の険しい山道は、時には敵を阻む要害となり、時に信仰の場となりました。そこに残された痕跡は、松尾の歴史や信仰を私たちに伝えてくれます。(宮津市教育委員会)

(朝日岳の行者堂)