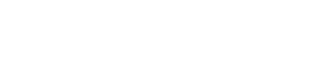本文
みやづ歴史紀行(146回)
慈眼寺と山林寺院の広がり
 慈眼寺観音堂
慈眼寺観音堂
世屋山慈眼寺は、上世屋集落の古刹であり、聖観音菩薩(しょうかんのんぼさつ)を本尊とします。現在は、本堂とその奥地の銚子(ちょうし)の滝の傍らに建つ観音堂が残ります。観音堂の周辺では、古くは雨乞いなどの神事が行われていました。また、江戸時代には、成相寺の奥の院とする伝承が生まれるなど山間部を通じた信仰の広がりが窺い知れます。
世屋や、隣接する野間(京丹後市)は、山深くに位置する地域的特色から、修行僧や山伏が足を踏み入れていたことが史料や伝承より知られており、古くは中世以前に遡ります。
建久三(一一九二)年に、 「野間世野(のませや)」の妙徳寺(みょうとくじ)と西芳寺(さいほうじ)という二つの寺院の復興を祈願した願文が見られます
(『 鎌倉遺文(かまくらいぶん)』六二四、六二五)。これらの史料より鎌倉時代以前には、周辺地域に寺院が建立されていたことが窺い知れ、地域の寺院の成立を考えるうえで重要な史料です。また、復興に際し、地域の有力者と見られる願主の活躍についても記されており、妙徳寺では、願主の一族と見られる丹波経成(つねな り) ・成行らが柿葺(こけらぶき)の五間四面(ご けんしめん)の堂一宇(どうい ち う)の再建、金色丈六薬師如来像(じょうろくや くしにょらいぞう)の修復安置や経典の奉納作善を行っており、西芳寺では、願主である伊津部恒光(い ちぶつねみつ)や、その一族らが病気祈願のため彩色(さいしき)丈六薬師如来像をはじめとする諸尊像を安置奉納しました。
この妙徳寺と西芳寺については、存 在した場所も含めて詳(つまび)らかではありません。しかし、願文から妙徳寺の本尊として創建時より観音菩薩を祀っていたことが記されており、平安後期に三十三所観音霊場(さんじゅうさんしょかんのんいじょう)として信仰を集めた成相寺の存在もあわせて、丹後における山林寺院や観音信仰の広がりを考える上でも興味深い存在です。
(宮津市教育委員会)